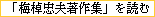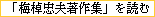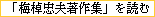
「梅棹忠夫著作集」を読む
2006/11/07(火)
「梅棹忠夫著作集」の
5巻:「比較文明学研究」を よみおえて、返却し、
13巻:「地球時代に生きる」を かりだして きました。
○5巻:「比較文明学研究」は、著作集の なかでも 最初に 刊行された 論文集です。 それだけに、研究色の つよい 独特の 梅棹流 文明学の 世界が 展開されて います。
○主要テーマは 「文明の生態史観」、「宗教の比較文明論への試論」でしょう。
○梅棹の 文明把握の しかた は、旧世界(新大陸:南北アメリカ大陸を除く)の文明を 単に 時間軸に ならべて 比較する のではない。 発生した できごとを 全部 ならべ、場所ごとに 比較して、 相違・合同・平行の 度合を しらべる という 方法を 丹念に 実行した ことだ。
おそらく、ユニークな(生物の生態学的アナロジーで) 仮説を 胸に ひめた うえで、取材カードを 丹念な 解釈を して あたらしい 文明論を 構築した のだろう。(取材カード 云々は わたしの 推測)
○旧世界を 楕円で あらわすと、左が西ヨーロッパ、右が日本。 この部分を 第一地域。 残りの 楕円大部分を 第二地域 とする。 旧世界を 2分する。(西ヨーロッパと 日本は 楕円では 分かれて いるが、おなじ 第一地域と 呼ぶ)
○文明の 似かよりで 2分した。 明治維新で 「西欧に 学ぶ」 ことが、スムーズに いったのは 社会制度など 経験の 歴史・積み重ねが 似たもの同志 だった からだ。
○今回、「宗教の比較文明論への試論」を よんで、梅棹文明学の 底力を 実感した。 旧世界の 宗教分布を 比較。
宗教の 定着・流転を 疫病の感染に アナロジー比較する という ユニークな 方法。 第一地域では、土着信仰→普遍信仰 の 2段階で 感染が 止まった。 第二地域では、土着信仰→普遍信仰→再帰信仰 の 3段階感染。
○第一地域は、西ヨーロッパ:民族信仰→キリスト教、日本:神々→仏教。 第二地域は、イラン・オリエント・地中海:古代信仰・ユダヤ教・神々→ゾロアスター教・キリスト教・キリスト教→イスラーム教、インド:バラモン教→仏教・ジャイナ教→ヒンドゥー教、中国:儒教→仏教→道教。
○第二地域は、古来の 4大文明 発祥の 地域。 普遍信仰が 流布した あとに、むかしの 信仰を 改変した 回帰・再帰信仰に 再感染・もどる 傾向が ある という。(簡略しすぎた わたしの 要約です)